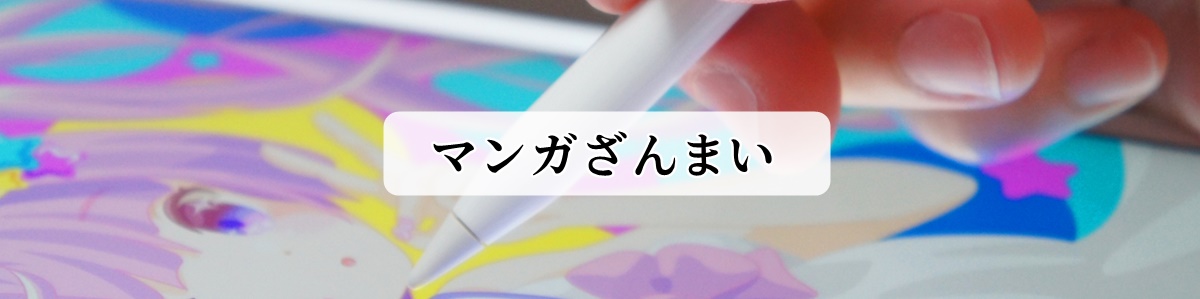
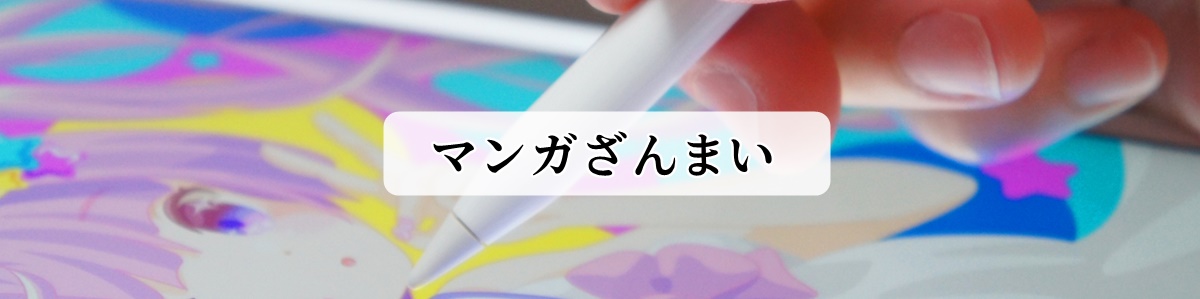
漫画の怪我の描き方
漫画の傷のサンプル
色んな漫画作品を調べて、傷のあるキャラを探すかぁ…と思ったら、クリスタに傷素材というのがありました。
とりあえずこれでいいかも。
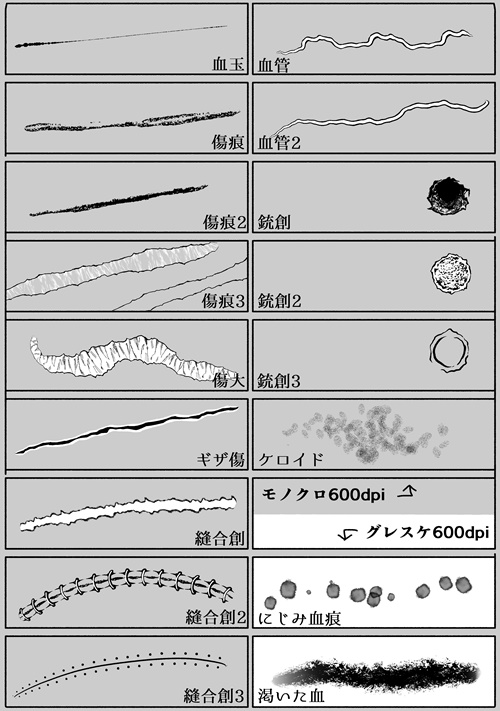
実際の傷がこんなふうになるのかはともかく、「漫画っぽい」傷跡が揃っています。
今斬られたばかりという感じの傷から、手当直後の傷、古傷までいろいろ。
顔に傷のあるキャラとかを作って、個性を出すのも良いかも知れないですね。
関連)キャラクター設定のやり方
漫画の傷跡の基本的な描き方
漫画で傷跡を描く際は、リアリティと読みやすさのバランスが重要です。
結局、リアルな傷を描いても画力次第では、「何が描いてあるんだコレ?」ってなっちゃうんですよね。
なので、あまり絵に自信がない場合は、最初から漫画的な傷を真似て描くのが良いかも知れません。
いちおう、傷のパターンはこんな感じ。
- 傷の種類に応じた線の使い分け
- 切り傷:シャープな直線
- 擦り傷:不規則な短い線の集合
- 刺し傷:中心が濃い点状の傷
- 傷の深さの表現
- 浅い傷:細い線で軽く
- 深い傷:太い線と影を付けて
- 傷跡の経過時間の表現
- 新しい傷:赤みを帯びた色
- 古い傷:肌色に近い色で薄く
- 周囲の皮膚の変化
- 腫れ:輪郭線を少し太くする
- 炎症:傷の周りに薄い赤みを付ける
漫画で見るのは、「切り傷」とかが多いですね。なんといってもわかりやすいから。
逆に「刺し傷」とか「すり傷」なんかは、よくわからないなんだコレ?と思われてしまう可能性もあります。
傷を描かない怪我の表現として、以下が使われることがあります。
- 絆創膏(小さな怪我)
- 包帯、ギプス(大きめの怪我)
- 腕を肩から吊る(骨折など)
- 病院のベッドで天井から足を吊る(足の骨折など)
大怪我を負って、包帯だらけの綾波レイ(エヴァンゲリオン)の人気が出たこともありました。(怪我ドル、という存在も当時少し流行りました)
#アーマードコア6
綾波レイ→包帯巻きの状態で運ばれる
621→冷凍マグロ状態で運ばれる
綾波レイ→単眼機を駆る
621→単眼機を駆る
綾波レイ→ゲンドウの指示で動く
621→ウォルターの指示で動く
綾波レイ→碇ユイの量産体の1人
621→強化人間の量産体の1人
綾波レイ→大人しい
621→大人しい pic.twitter.com/JKmUBoElWf— 広告と戦う実況者ミスニージュ (@Misnieju) July 27, 2023
漫画の血液表現のテクニック
血液の描写は、漫画の怪我シーンにおいて重要な要素です。リアルな血液表現のためのテクニックをいくつか紹介します:
- 血液の粘性を意識する
- 垂れる血:重力に従って流れる曲線
- 飛び散る血:不規則な形状の飛沫
- 血液の量による表現の変化
- 少量:点状や細い線
- 大量:面積の大きな塗りつぶし
- 血液の経過時間による色の変化
- 新鮮な血:鮮やかな赤
- 時間が経った血:暗褐色
- 血液が付着する表面の質感
- 布地:にじみや染み込み効果
- 金属:光沢のある滴状
- トーンやスクリーントーンの活用
- 濃淡:血液の厚みや量を表現
- パターン:血液の質感を強調
斬られて血がブッシャー!と飛び散る。派手な演出シーンですが、アニメなどでは血しぶき演出が抑えられる傾向にあるようです。
実は、1990年代~2000年代初頭は、アニメや漫画のち飛沫表現はかなり厳しかったみたいですね。血の色を赤ではなく、黒や白で表現したり、残酷シーンカットなどの対処が一般的でした。
でも、最近は、当時よりは規制がゆるくなっている気がします。
深夜アニメ枠だと、鬼滅の刃とか、チェンソーマンなど。けっこう血がドバドバ、首が斬られたりとかするんですが、わりと不自然な規制をされてる感じはしません。
海外アニメだと、血が出ることにたいして、だいぶ厳しいみたいですね。
SNSでは、血しぶきが含まれるイラストには「流血注意」などのタグがつけられて、「苦手な人は気を付けて!」という配慮が行われているみたいです。
ちなみに、血しぶき規制は、特に法律に沿ったものではなく、テレビ局の自主規制っぽいですね。
漫画の怪我シーンの効果的な演出方法
怪我シーンを効果的に演出することで、読者の感情を揺さぶり、物語への没入感を高めることができます。
- コマ割りの工夫
- 大きなコマ:重要な怪我シーンを強調
- 小さなコマの連続:怪我の瞬間を細かく描写
- アングルの選択
- クローズアップ:傷の詳細を見せる
- 俯瞰:怪我の全体像や状況を把握
- 効果線の使用
- 集中線:衝撃や痛みを強調
- スピード線:動きの速さを表現
- オノマトペ(擬音語・擬態語)の活用
- 「ドクッ」「ズキズキ」:痛みを表現
- 「ドバッ」「ビチャッ」:血液の音を表現
- キャラクターの表情や仕草
- 痛みに耐える表情:歯を食いしばる、目を見開く
- 身体の反応:傷口を押さえる、体を丸める
- 背景の処理
これらの要素を適切に組み合わせることで、読者に強い印象を与える怪我シーンを演出できます。ただし、過剰な表現は避け、作品全体のトーンとバランスを取ることが大切です。
漫画の怪我描写における解剖学的知識の重要性
リアリティのある怪我の描写には、基本的な解剖学の知識が不可欠です。以下に、漫画家が押さえておくべき重要なポイントをまとめます:
- 筋肉の構造
- 表層筋と深層筋の違い
- 主要な筋肉の位置と形状
- 骨格の理解
- 主要な骨の名称と位置
- 関節の動きと制限
- 血管の配置
- 動脈と静脈の違い
- 主要な血管の走行
- 皮膚の構造
- 表皮、真皮、皮下組織の層
- 皮膚の厚さの部位による違い
- 内臓の位置
- 主要臓器の配置
- 臓器損傷時の影響
これらの知識を活用することで、怪我の種類や程度に応じた適切な描写が可能になります。例えば、切り傷の深さによって露出する組織が異なることや、打撲による内出血の広がり方などを正確に表現できます。